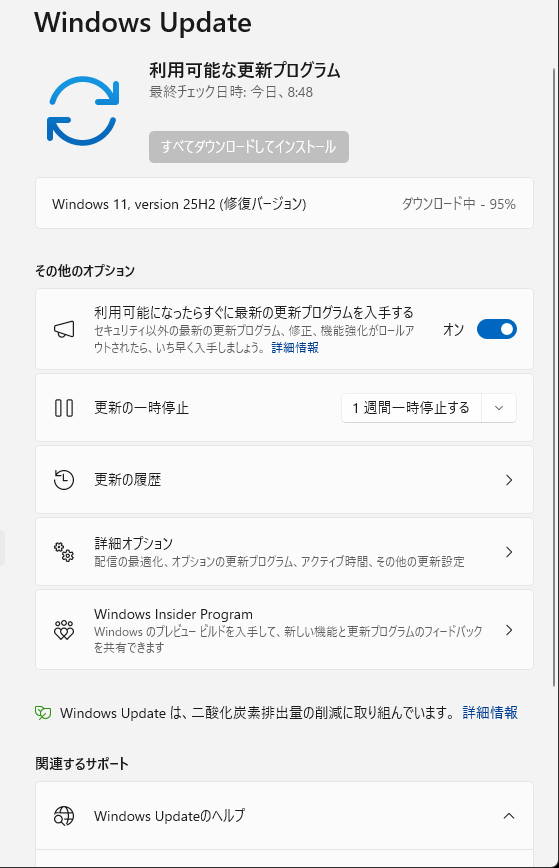何年か前にデフリンピックの記事を書いたので、絶対に行って見ないと!と思ってました。一昨日にサイクルスポーツセンター、今日は駒沢オリンピック公園へ行きました。応援というか観戦というか、そういう目的もあるのですけれど、「耳が聞こえない」状態でどのくらい支援や工夫が必要なのか?ってのが最大の関心事です。
自転車競技はサイクルスポーツセンター、伊豆の山の中で行われています。高校の遠足で来たのが最後のような気がします。記憶に2シーン残ってました。公共交通機関はやめたほうが良いかなぁという場所です。


天気は良かったのですが風がとっても強くて、帽子は飛ぶわパンフは飛ぶわ…山中だけあってホコリが舞うことはなかったし、混雑はなかったので観戦自体は良かったです。
定型者競技との違いですが、フラッグの活用が大きいのかなぁ?あと誘導する人の体の動きが大きくてわかりやすいとか?指示が手話だったりライブ画にテロップが入ったり…聞こえないから視覚支援というのは当然なのですが、違和感なんて全く無いですし定型者競技でもこのくらいやれば?と思いました。
そして本日の駒沢オリンピック公園。

陸上はスタート合図で光を使っていました。

バレーボールは久しぶりに見たのですけれど、ルール変わった?昔、小学生チームの指導なんかしていましたが、得点の入り方やラインズマンの仕草が違う?
プレイ中の指示が難しいのかなぁとは思いましたが、定型者とあんまり変わりがないかなぁと思います。選手間でのやり取りが手話という点はありますけれど。

ハンドボールなんか見たのは子どもの頃?とにかく久しぶりですが面白くて今日の競技で一番時間をかけました。
試合中の指示がバレーより困難になっていますね。バレーは対面で陣地が分かれていますが、これは混戦なので、より注意が発信者に向きづらいようです。面白いなーと思ったのは、監督さんや控え選手がエキサイトして怒声をだしていたシーンですね。国際大会でもこんなシーンを見れるんだぁ。
スポーツ系の競技大会はかなり大きな応援の音がしますが、最初の自転車競技はとても静かでしたし、今日の3競技もそこそこな応援の音はしますが、定型者競技ほどではなかったです。自分としては程よく観戦できるので良いポイントでした。
会場内で選手も観客も手話コミュニケーションが多かったなぁ。外人さんも手話の人が多かったなぁ。手話で会場スタッフに文句をいっている人もいましたね。状況や手話を見て何となく内容がわかるのも面白かったです。

教育流れで見ると、うにばーさるでざいんでハードルを低くした上で個別支援というのが主流になるのかな?だとすると視覚支援が可能な競技は分けなくても良いように思います。オリンピックがそういうアピールをすれば、支援の思想が広がると思うのでやってほしいとは思いますけど、実際には色々絡んで難しいのでしょう。今回、実際に観戦してオリンピックともパラリンピックとも分けている意味もわかった気がします。
日本初開催でありますし、初回から100年目の節目でもあるそうです…ということは初回は昭和元年だったのかな?11月26日が閉会式なのでその前日までが競技期間になります。国際大会にしては混雑もしていませんので、ぜひ観戦をすすめるのであります。でも週末は混むのかなぁ?ライブ配信もしていますよ。
日程表は
https://deaflympics2025-games.jp/news/docs/JP_TOKYO2025_Competition_Schedule02.pdf.pdf